※この記事は「隅っこのおすすめ書籍」という意味で、広告的な要素を含みます。
こんにちは、花粉に苦しむ隅っこです。
花粉・・・最近酷いですね・・・。。
花粉症っていうのもあるけど、アトピー性皮膚炎なので、この時期は何かのきっかけでアトピーが悪化しやしないかと、戦々恐々としております。。
さて、隅っこのXをフォローしている方はご存知かもしれませんが、隅っこが通っているカウンセリング講座の中越先生が、最近新刊を出されました(`・ω・´)
タイトルは「傾聴の極意」
先生が初めて”カウンセリング”について書かれた書籍ということで、発売前から興味津々だったし、めちゃくちゃ楽しみにしてました(*´艸`*)
今回は、この本を読んで心に残ったことや、自分自身の気づきをまとめてみようと思います。
でも、一番言いたいことを先に書いちゃうとね・・
「先生と出会えて、先生の講座に通えて、よかったな」
「傾聴の極意」全体のざっくりした感想
傾聴の極意は全体を通して柔らかく、温かい語り口で、とても読みやすかったです。
講座で聞いた内容もたくさん入っていて、なんだか講座を思い出して懐かしくなりました(´∀`*)ウフフ
それに、恐らくこれから学ぶであろう内容も書かれていて、ばっちり予習もできちゃう・・・お得な一冊でした。
特に隅っこは、「はじめに」の一番最初に書かれた、とある一節がお気に入りです。
本書は、あなたの「傾聴するこころ」を育て、人生を豊かにする本です。
ごめんなさい。すぐ使える「傾聴のテク」は紹介していません。
傾聴は「人としての在り方」だと、僕は考えているからです。
「はじめに」の時点で「テクは書かないよ」と断言されているのをみて
「売るためじゃなく、本当に伝えたいことを詰め込んだ一冊なんだな」と感じたし、
「この本は中越先生らしさが詰まっているに違いない」と、ものすごくワクワクしました。
最近は「傾聴」ってビジネスの世界でもよく聞くようになったけど・・・、そういう文脈で言われる傾聴って、なんとなく「相手をうまく動かすため」みたいな要素がある気がしてます。
もちろん、それが悪いわけじゃないし、必要な場面もあると思います。
でも、今回先生が書きたかったのは、そういうことじゃなく、「傾聴する」という行為の裏にある”信念”や”理念”みたいなものを書きたかったのかな、と思いました。
実際に書籍を読んでみても、一貫して「ハウツー」みたいなことは書いてなくて
「なぜ、傾聴をするのか?」
「何を目指して傾聴するのか」
「そもそも傾聴とはなんなのか」
そういう”本質”に関することが、丁寧に丁寧に書かれている、そんな素敵な一冊でした。
特に印象に残った個所
ここからは、書籍のなかで特に印象に残った部分について、書いていこうと思います。
ただ、注意点として・・おそらくめっちゃ長くなるのと、少し”隅っこの暗い部分”が出てくるかと思います。
なので、元気なときに流し見程度でご一読いただけると幸いです。
「愛」ですか・・・?
隅っこが頭ぶん殴られるレベルで衝撃だったのは・・
第一章の「受容、共感、自己一致」に関する部分です。
受容とは、相談者さん、クライエントさんの考えや感じていることを、それがどんなことであっても、受け入れる、ということ。
共感とは、相談者さんの感じていることを、カウンセラーが想像し、相談者さんと同じように感じて、同じ景色を見ようとすること。
自己一致とは、カウンセラーが自分自身が感じていること、考えていることから目をそらさず、ごまかさず、正面から受け止めること。
(あくまで、隅っこの解釈です)
たぶん、カウンセリングを学んだことがある人なら、一度は聞いたことがあるであろう、この3条件。
この3つがそろっているカウンセリングは、うまくいく、そんな風に言われています。
そして、中越先生はこれら三つの条件について、以下のように書かれていました。
しかし、この「受容」「共感」「自己一致」は、決して足し算できるようなものではありません。
本来もっとひとつのもので、混ざり合い、溶け合って、決してバラバラに語ることができないものです。その姿を、もっとわかりやすい言葉で表現するなら、それこそが「愛」というものなのかもしれません。
「・・・・愛、ですか??」
この一文を最初呼んだとき、思わずそう呟いてました。
電車内で読んでたけど、同じところ何度も読み返して、10分くらいあほみたいに突っ立ってました。
実際、たぶん、あほ面していたと思う・・(;^ω^)
こういうと「冷たい奴」と言われるかもしれないけど・・・
隅っこは恋愛感情とかが、正直よくわかりません。
世間一般で言われる「愛」とやらも、いまいちピンとこない、というのが本音です。
それでも、隅っこもこれまでの人生の中で、たまにではあるけど、この3条件に近い感覚を味わうことがありました。
損得とか関係なく、目の前の人をただただ理解したいと思う、
その人が感じていることを、ジャッジせずに聞きたいと思う、
そしてうわべではなく、本心からの言葉を渡したいと思う。
いつもいつも、そんなちゃんと聴けてるわけじゃ全くないけど、
それでも「そうありたい」という気持ちをもつことは、昔から少なからずありました。
でも同時に、それを感じるとき、ちょっとした”罪悪感”も常にセットでした。
理由は色々あるけど・・一言で言うなら
「そんな感情、綺麗ごとだ」
と思っている自分がいたから。
「そんなお人よしじゃ、将来利用される」
「そんなの偽善だ」
そう言われてきたから。
だから、そういう感覚を感じるたび、自分が偽善者のように思えて、嫌になりました。
でも、中越先生はそれを「愛」だと言い切った。
「愛」ですか?私がもっとも理解できないと思っていた感情?
それをすでに私は知っている??
ちょっと色々パニックで、しばらく唖然としてました。
なんというか・・・掴みはバッチリ過ぎますね。。
(ここで引っ掛かるやつ、たぶんいない。。)
自分の感じたことのあるものが「愛」なのかどうかは、いまだにわかりません。
でも、ちょっとだけ「愛」に対する距離が縮まったと思います。
もう一人の自分がいる・・・って、そうなるの!?
もう一つ、傾聴の極意の中で衝撃を受けた部分があります。
それは、中越先生のカウンセリング「ホープセラピー」の原体験となるお話に関してです。
先生は「アルコール依存症」のご家庭で育ち、先生の日常はお酒と暴力があふれかえっていたそうです。
明かに過酷で、生き延びるのだけでも大変な環境。
そんな環境だったから、思春期を迎えるころには、すでに「死にたい」という感情を抱えていたそうです。・・・まあ、そうなっても不思議じゃないよね。
毎日毎日、「心臓止まれ」と毎晩布団の中で心臓に命令していて
でも、それでも自分の心臓は止まらなくて、
髪の毛だって真っ白になったりしなくて
お腹だって空いて・・。
そんな自分を見て、先生は
こんなクソみたいな人生でも、生きた方がいいと思っているもう一人の『僕』
がいる、と気づいた。
そして
だったら、そっちの『僕』が見ている生きた方がいい人生って、どんなものなのだろうか。実際に見てから死んでやろう
と考えるようになった。
正直に言いましょう・・・このお話を見たとき、隅っこは
「そっちの発想いったの!?Σ(゚Д゚;≡;゚д゚)」
と思いました。
私もこれまでの人生で「終わり」に手を伸ばしたい、と思ったことが何度かあります。
そして、そう思いつつも、自分の身体が空腹を訴えたり、眠気を感じたりすることに対して、
「身体反応は・・こっちの気も知らないで・・」
と冷めた気持ちを持っていました。
もっと言うと
「生きようとする反応が出てる時点で、本当は苦しくなんかないんじゃね?」
と思って、自分の苦しみを否定していました。
だから、中越先生の「生きようとしているもう一人の自分」という発想を聞いたとき
「その発想はなかったぞ!?」
と衝撃でした。
希望をもって、生きようとしている自分がいる。
もう一人の自分が「死ぬのはまだ早いよ。もう少し、生きてみようよ」って言ってくれてる。
そんな風に考えたことなかったし、その考えは・・ちょっと素敵だな、と思いました。
そして、「素敵だな」と感じられた自分に対して、ちょっとビックリしました。
たぶん、前までなら「そういう考え方ができたら、いいんだろうけどね・・」と、全く響かなかった気がします。
カウンセリングを受けて、カウンセリング講座で心理を学んで、色んな人と関わって・・ちょっとずつ変わってるのかな。
傾聴の極意を読んで、改めて思ったこと
傾聴の極意を読んでいて、思い出した先生の言葉があります。
「僕たちカウンセラーは、相談者さんのネガティブだけじゃなく、ポジティブにも寄り添うのが大切なんです。」
これは、講座の初期で隅っこがロールプレイの相談者さん役をしたとき、
中越先生からもらった言葉です。(先生がカウンセラー役をしてくれた)
ロールプレイでは、隅っこの過去の傷について、少しだけ触れました。
そのうえで、隅っこが「今やりたいこと」についてお話をしました。
過去の傷に関して、あれこれ深堀することもできたはずです。
というか内心、そういう展開になったらどうしようかな、と心配してました。
でも、先生はそれをせずに「今やりたいことを」に焦点を当ててお話を聴いてくれました。
そのうえで、
「今やりたいことを少しずつでもやるには、どうしたらいいのか」
を一緒に考えてくれました。
確かに自分には「心の傷」がある。
でも、私が今話したいのはそれじゃない。
「今やりたいこと」は心の傷や、思考の癖の影響も、確かにあるかもしれない。
でも、それでも確かに、今、私自身はそれを「やりたい」と感じている。
先生は、そこにしっかりと光を当ててくれた。
「心の傷があるから、そう考えちゃうんじゃないか」みたいな分析、一切しなかった。
ただ純粋に「あなたは今、それをやりたいんだね」って、お話を聴いてくれた。
そのことが、とても嬉しかったし、
それこそが「ポジティブにも寄り添う」ってことなんだと思いました。
心の傷があっても、何かしらの特性の偏りがあっても、それがその人の「全て」じゃない。
その人は、その人なりに何かしらの「希望」を持っている。
その希望の芽(ジャガイモの芽)を、一緒に見つけていくのが
カウンセリングや傾聴なんだと思いました。
(もちろん、そのためにはネガティブな部分にも寄り添うのが大事。)
最後に
先生の新刊「傾聴の極意」を読んで、改めて「中越先生に出会えて、よかったな」と思いました。
ただ心理学の知識や理論を学ぶだけなら、書籍でもいいし、もっと「知識中心」の講座でもいい。
でも、私が最も求めていたのは、そういうことではなかった。
じゃあ、なんなんだ?って言われると・・なかなか難しいけど・・。
あえて言うなら
「人と人との温かな交わりが、どのようにして人の心を癒すのか」
ということなんだと思います。
ロジャーズさんの教え子である、デイブ・メアンズさんの言葉を借りるなら
「深い関係性」・・・になるのかな?
深い関係性が、いかに人の心の癒しにつながるのか、それが知りたかったし、今も知りたい。
そして、それは「教科書通りのお利口な講座」では決して得られない。
自分の言葉でカウンセリングを語れる人、
自分の信念をもって相談者さん・クライエントさんと向き合える人からでないと、決して学べない。
だから、本当に中越先生に出会えて、先生のカウンセリング講座に通えて、よかったな、
と心の底から思いました。
・・・あはは、長くなっちゃった。
以上、隅っこの「傾聴の極意」感想でした。
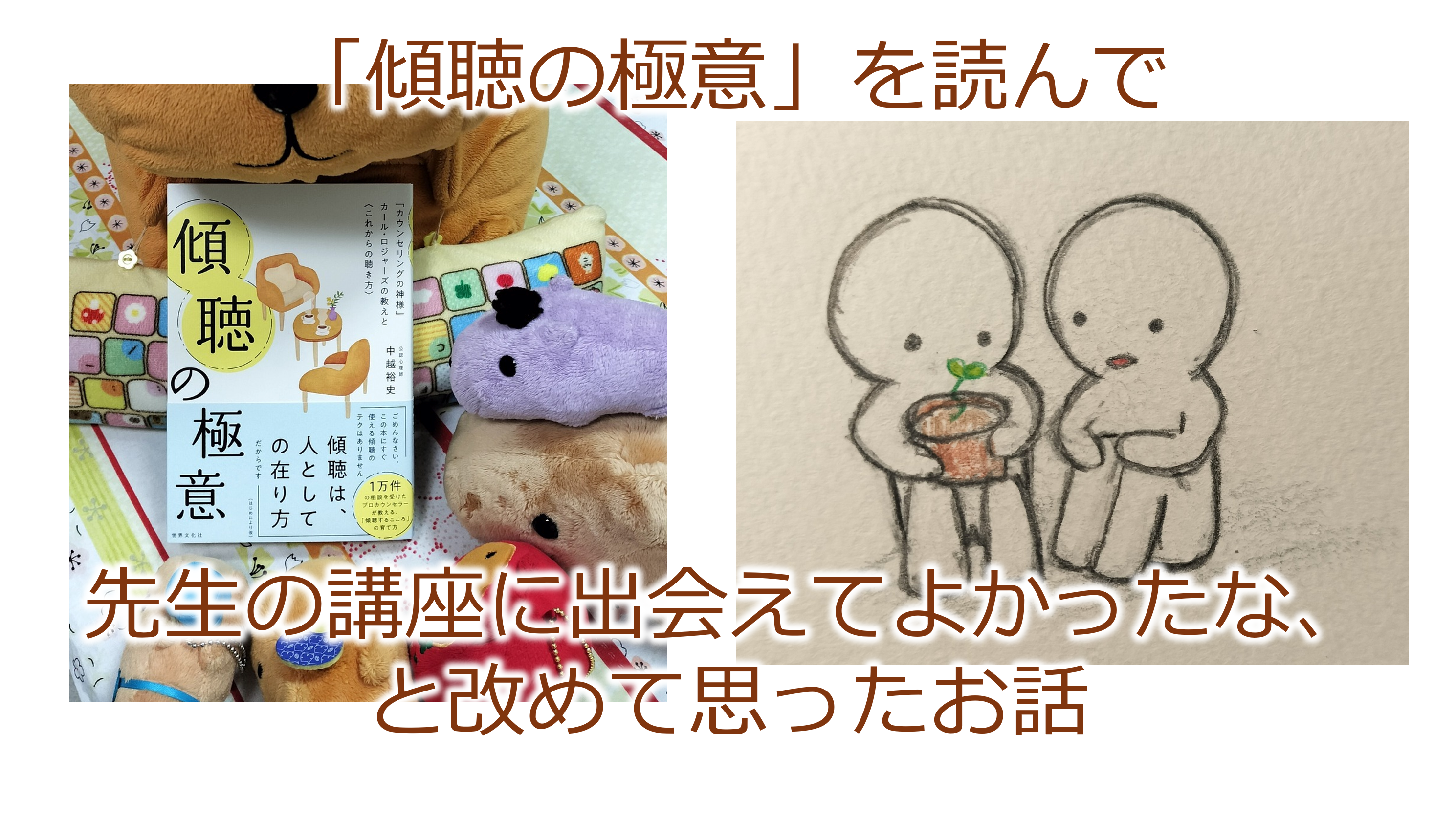
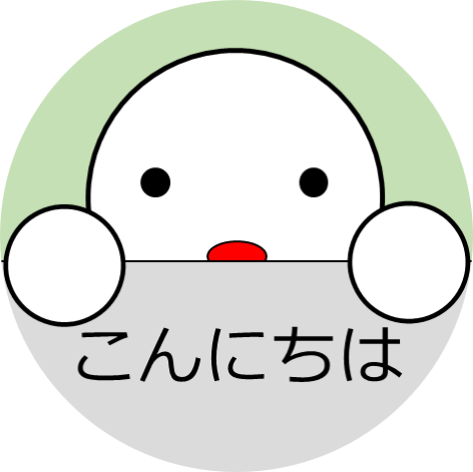

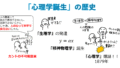
コメント